期末テストが終わった。
1週間に及ぶテスト期間は、耐久レースのよう。勉強するにも、集中力を保持するにも体力が必要なのだとしみじみ思った。難しいことを考え抜いていると本当に疲れる。そして別のことを考え出す。そして気が紛れたらまた問題へ。自分の集中力をなんとか飼い慣らしながら、マークシートを塗りつぶす。
テスト終了後は教室にて何名かのクラスメイトと「あの問題の答え、何だった?」とワイワイ騒いで一喜一憂する。中には資料や教科書をめくっても、ネットで調べてもはっきり答えが出てこない問題もあり、みんなであーだこーだ言うのもまた面白いものだ。
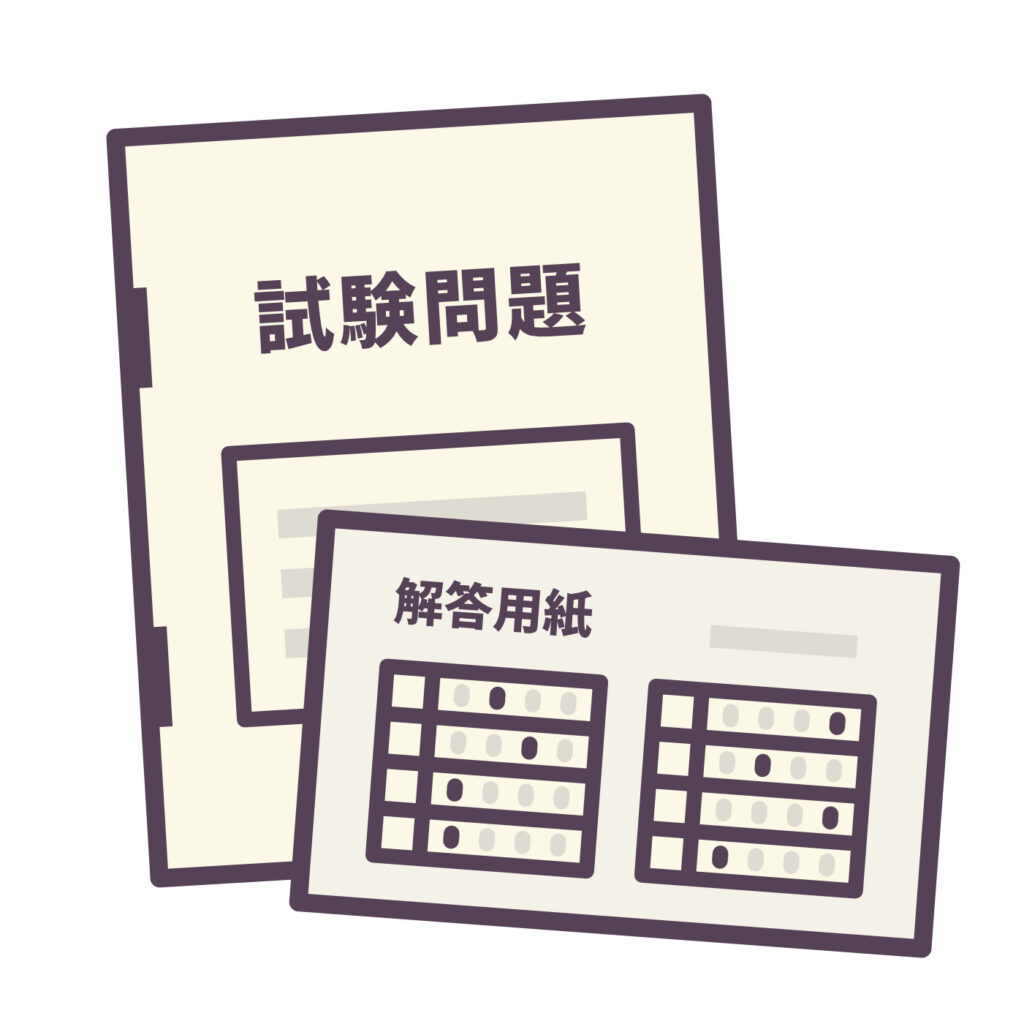
テスト終了と共に、弟が5歳の姪っ子を連れて我が家へ。しばしかわいいお客さんに翻弄される。姪っ子はかなり弁が立つ。5歳とは思えない語彙能力だ。
敷地内で見つけたほおずきを2つ摘んで渡してやると、「こっちは振るとカラカラする~。でもこっちは振っても何の音もしないのはなぜ?」と、質問してくる。中身の種がどうなってるかの違いじゃないの?と言うと、早速音がしない方のほおずきを分解。「あっ、中からこんなミニトマトによく似たのが出てきた!これが種?!」と言って大喜び。

小学校入学前にしてもうひらがなもカタカナも読めるらしく、一緒に居て会話がつきない。2歳頃からかなりベラベラしゃべる子だったから、お年頃になったらどんな会話ができるか楽しみだ。
さて、タイトルの「虚実」について書いてみようと思う。
東洋医学において、
・虚とは、必要なものが足りない状態。
・実とは、余計であったり過剰であったりする状態。
というような意味合いで語られる。
東洋医学は、何ともファジーな部分があるので、「虚は数値○○以下、実は数値○○以上です。」とか言えない。約2000年前に生まれた学問であるが故、それはそうだろう。またこの学問、物質や物体や数値でなく、状態やはたらき、存在を指して語られる事が多い。よく言えば広い視野から物事を捉えている、悪く言えばぼんやりしている。
でも、日本に生まれ日本に育った人ならば、感覚的に分かるのではないか。
虚でもなく実でもない、中庸な状態、それを「平」とよぶ。それこそがいい塩梅の健康な状態なのだ。